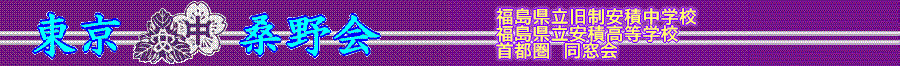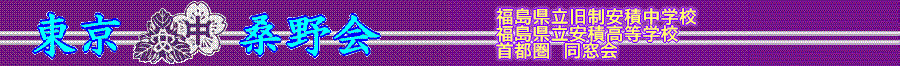71���@���J�N�v
�i������ƎႢ?�j |
2008.06.07�@�u���W���R�[�q�[�@�F�@���{�l�̂P�O�O�N
�@�@�@�@�@�@�@�@�|�u���W���Ŕ����I�A���{�l�ō��̃R�[�q�[����z�����_��傩��̎莆�|
���J�N�v�i�����_�H��w���_�����A�S��AJATAK�Q�^�j���̘A�ڂɂȂ�܂�
��JATAK�F�_�ƋZ�p���y�𗬃Z���^�[
�}�ˊ�
�@���{�l�̏��߂Ẵu���W���ږ��D�u�}�ˊہv��1908�N6��18���ɃT���g�X�̍`�ɒ������B���N�̓u���W�����{�l�ږ�100���N�ɓ�����B������L�O���Ă��܂��܂Ȏ��g�݂��s����B
�@2���̃u���W���E���I�̃J�[�j�o���ɂ́A�u�}�ˊہv���e�[�}�ɁA�����Ԃ���i�A�啧�l�Ȃǂ̓��{�������ے��������������{�̂����̂��f�U�C�������ߑ��̃_���T�[��z�����R�Ԃ��o�ꂵ���B�u���W���̃T���o�`�[���ɓ��n�̐l�X���Q�����ăp���[�h����p�����{�̃e���r��V���i�w�����E�[���x2008.2.4�Ȃǁj�ɕ���Ă����B"���[�b�A�u���W���ł͐���オ���Ă���ȁ["�ƁA�����̑O�܂Ō��n�ɂ������̂Ƃ��Ă͂킭�킭�����v���������B���ꂾ���u���W���ł͓��{�l�c�m�`�E���{�������u���W���Љ�ɁA�u���W�������̍\���v�f�Ƃ��āA�������荪�t���Ă���̂ł���B
�@����ɂ���ׂ���A����o�������̓��{�ł͂��̋C�z���Ȃ��c�Ƃ�т����C�����ł�����A�������A�u���W������̗A���R�[�q�[�ɒ[�����R�[�q�[�ƊE�͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�L�O���i���o���Ă��邱�Ƃ�m�����B�����������ꂵ���Ȃ��āA�����A��������ɓ��ꂽ�킯�ł���i�ʐ^�j�B
�@�������͊��Ԍ���ŃR�[�q�[���w�u���W�� �V���T�J�_���x�A�ʃR�[�q�[�w����T��BRAZIL�x������u�V���T�J�E�^�_�V�v�̎ʐ^����Ŕ��������B
�@�L�[�R�[�q�[�͓��{�l�̃R�[�q�[���Y��100�N�̑��Ղ�H�����w���{�l�u���W���ڏZ100���N�L�O�V���[�Y�x��̔����Ă���B�@
�R�[�q�[�͓��{�l�ƃu���W�����Ȃ����J
�@���{�l�ږ��̓R�[�q�[���̃R���m�i�J���ҁj�Ƃ��Čق��Ă͂��n���̗����܂ŊC��n���čs�����B����́A�����̍������ɂ߂����{�̒����������猾������A�u���W��������{�Ɏd���肪�ł��āA�܂��_����Ԃ��ߏグ����̋��ɋтŋA���ł���Ǝv�킹��悤�Ȍ_������ł���������ł������B�قƂ�ǂ̈ږ��͏o�҂����ړI�ł������B
�@�������A�����ɂ͂���Ȃ킯�ɂ͍s�����A�����u���W���ŁA�Ȃ�Ȃ��J���A�������������̂��߂ɁA�z�����ꂽ�_�ꂩ�瓦���o������A�}�����A��a�ɓ|�ꂽ�肵���l�X�����������悤�ł���B�������͐ΐ�B�O�́w�����x�i1935�N�D��1��H��܁j��k�m�v�́w�P����ɂ���̉��Łx�i��1���C1982�j�ɕ`����Ă���B���̈���A���̎��������z���āA�R�[�q�[�͔|�̋Z�p��g�ɕt���A������~���āA�R�[�q�[���̘J���҂���A�u���W���̑�n�ɍ��������āA�������Ȃ�����Ɨ��̔_���o�c�҂ɂȂ����l�X�����������B���{�l�́A������������邾���̃R���m�ŏI���͂��Ȃ������̂ł���B�s���s���̐��_�A�D�ꂽ�m�͂ƋZ�����Đ������������̐l�X�����Ȃ�������A������150���l���z������{�lDNA���������l�X���u���W���ɂ���킯���Ȃ��̂ł���B���̂��炵���������ږ��̍����E�ߎS���̋����̉A�ɉB��ĈӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B
�@���̕ӂ̎���x���m���́w�u���W���E�R�[�q�[�̗��j�x�i1973�N�C�T���p�E���j�ɋ�̓I�ȃf�[�^�[��t���Ă悭������Ă���B���Ȃ킿�u�c�R�[�q�[�������������Ƃ������{�ږ��́w���O�x�́A�킸���̔N���Ō����Ɏ������B��1��ږ��������Ă���15�N���1923�N����A�M�l�̃R�[�q�[�A�͎����͂��ł�2500���{�𐔂����B������1928�N�ɂ�4000�{�ɒB���A����Ɉږ�25���N�Ղ̍s��ꂽ1932�N�ɂ́A����6000���{�ɒB���Ă����B�܂�A25�N�Ԃ�1���{�̏��k�傪6��l�ł����킯�ł���B�v
�@1932�N�܂œn���҂�11��5��l�A2��1��Ƒ��B���̂�����4����1��5132�˂��y�n���L�_�ƂɂȂ��Ă���i�T���p�E���_���Ȓ��ׁj�B�R�[�q�[�_�Ƃ�59���A�R�[�q�[�ȊO�̔_��ڂ́A�lj�14���A�R��8.3���A�ߍx�앨13���A���̑�5.7���ł������B
�@�A���t�����Ă����R�[�q�[���͑��v62,213�{�ŁA15���{�ȏ�̑傫�ȉ��̌o�c�҂�5�l�A10���{�ȏオ10�l�A5���{�ȏオ65�l�������Ƃ������Ƃł���B�܂��ɁA�R�[�q�[�̂������œ��{�l�ږ��̕�炵�����藧���Ă����̂ł���B�R�[�q�[�������A�u���W���Ɠ��{�l�������J�ł������ƌ����悤�B
�@���̌�A1929�N�̐��E���Z���Q�A�ߏ萶�Y�ɂ��R�[�q�[���i�̖\���Ȃǂ��e�����ăR�[�q�[�_�Ƃ�39���Ɍ������A�����ĖǍ�_�Ƃ�39���ɂȂ��Ă���B�܂��A����E���A�R�[�q�[�s�U�������ăR�[�q�[�_�Ƃ�24���ɂ܂Ō����������A1958�N�ɂ�28.3���ɂ܂ʼn��Ă���B���̊ԁA���{�l�̓T���p�E���ߍx�Ɉړ����i�݁A�����Ŗ�A�ʎ��A�ԂȂǂ̋ߍx�^�_�Ƃ�W�J���A�Y�Ƒg���i�R�`�A�A�X�[���E�u���W���Ȃǁj���������A�T���p�E���̐��N�H�i�s��ɁA����ɂ̓u���W���S�y�̔_�Y�H�i�s��ɑ傫�ȗ͂�����܂łɂȂ�B�܂��A�_�ƈȊO�̐��Y�A�Љ������ɂ��i�o�����B�������āA�}�ˊۈږ����琔���č����܂ł�100�N�ɂ킽���āA���{�l�A����DNA���������l�X�́A�u���W���Љ�̔��W�ɑ傢�ɍv�����Ă����̂ł���B
"�u���W���̌Z�M"����̎莆
�@���āA�������ɓo�ꂵ�Ă���V���T�J�_���̉��⋧����͎���"�u���W���̌Z�M"���ł���B"���߂łƂ�"�̃��[����ł�����A���������A�ނ��炤�ꂵ���ԐM���[�����͂����B
�@�u���̂Ƃ���A�J�͏����B�哤��g�E�����R�V�A�R�[�q�[�͂܂��܂��ł��B3��������5�����܂ő哤�A�g�E�����R�V�̎��n�B6���`9�����߂̓R�[�q�[�̎��n�B"�ǂ������A��������"�ƌ����Ȃ���52�N�ɂȂ�܂����B�v
�@�u52�N�O�A�A�����N�A�����̃W���[���X�ɂēƗ��B18�N�ԁA���N300�U�O��̐��I�ł����B�ł��A���̓����͑�_��ɂȂ����C�����ł���܂����B��������݂͌��邱�Ƃ��ł��܂���B�v
�@�����Ɓi���ܘY�v�Ȃ�5�l�̌Z��j�͕��������킫�s�̏o�g��1956�N�Ƀu���W���ɓn��A�T���p�E���B�J�t�F�����W���̐�O�ږ��̕����_��ŃR�[�q�[�͔|���w�B�����āA���݂̓~�i�X�W�F���C�X�B�J�����E�h�E�p���i�C�[�o�́u�t�@�[���_�E�p���C�[�]�v��450�w�N�^�[���̃R�[�q�[���𒆐S�ɁA�哤�E�g�E�����R�V�E�̗��{�{�Ȃǂ̑����_�Ƃő傫�Ȑ��ʂ������Ă���B1989�N����͓��{�Ɂw�J�����E�V���T�J�x�u�����h�Ő�����A�o���Ă���B
"�R�[�q�[�̕��Q��"
�@���₳��̎莆�̖����́u��������݂͌��邱�Ƃ��ł��܂���v��1�s���A�u���W���̃R�[�q�[���Y�̗��j�����ǂ�Ƃ��ɁA���́A�傫�ȈӖ�������̂ł���B�u���W���̃R�[�q�[�̏ꍇ�͎Y�n�̈ړ��������قǂ͂����肵�Ă���̂ł���B"����܂ł͌��n������̍L��ȃR�[�q�[�����L�����Ă����̂ɁA�����͈�{�̃R�[�q�[�̎��������Ȃ��B�����āA�ǂ����������ꂽ�Ƃ���ɍ��R�Ƒ�Y�n���o���オ���Ă���B"�ƌ������ƂɂȂ�̂ł���B����ɔ����Đ��Y�҂��勓���Ĉړ����Ă���̂ł���B�u���������R�[�q�[�i�Y�n�́j�ړ����A������̂�"�R�[�q�[�̕��Q��"�ƌĂ�ł���v�i�x���m���C�O�o�j�B
�@�Ȋw�I�ȍ����͖��炩�ł͂Ȃ����A�@����Ƃ���A���X�Ɣ엀�ȓy�n�����߂ăt�����e�B�A���Ă䂭�A���n�v�����e�[�V�����^�̊J��_�Ƃ̎p�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�u���W���ɂ́A�u�e���E���b�V���v�i���F�̓y�j�ƌ����鐢�E�I�ɗL���Ȕ엀�y��̂����z���Ă��邪�A�����ł́A���엿�Ő��\�N�ɂ��킽���č������ʐ����ō앨������B�������A�������̃e���E���b�V�������\�N���̎��D�_�Ƃɂ��炳���ƁA�{���ቺ��a�Q���̏W�ςȂǂɂ���Ēn�͂������āA�e���_�Ƃł͌o�ϓI�Ɉ�������Ȃ��Ȃ��������Ă��܂��B�R�[�q�[�Ɍ��炸�A���^�⍒���ł����肤�邱�Ƃł���B�������Ă���ƁA���Ă̔_�Y�n�т��A���ł͂܂�ȕ��q��������H�ނ����̒ᐶ�Y�͂̃p�X�g�i���n�j�ɂȂ��Ă���Ƃ���ɏo��B
���{�l�̃R�[�q�[���Y100�N�̑���
�@�u�L�[�R�[�q�[�v�̃V���[�Y�́A�u���W���ł̓��{�l�̃R�[�q�[���Y�̕ϑJ��H���āA���̎���ɂ䂩��̏��i�������̔�������̂ł���B���̎���敪�͎��̎l�ł���i�z�[���y�[�W������p�j�B�@"���̎���"�F1908�`1918�N�D�ŏ��̈ږ����_���J���҂Ƃ��Č_��ٗp���ꂽ����B�@�A"�J��̎���"�F1920�`1974�D�����̓y�n�����߂�ږ����������A�n����ړ��B���W�c���n�Љ�����n�߂�����B�B"����̎���"�F1975�`1985�N�D�Z���[�h�J�����Ƃ��n�܂�A�L��ȓy�n�ɖ���y�����l�����̋�J�E�w�͂̎���B�C"���n�̎���"�F1986�`���݁D���݁c�X�y�V�����e�C�R�[�q�[�Ƃ��Ė������Z���[�h�i���p�҂��ꕔ�����j�B
�@���₳��́A���̃L�[�R�[�q�[�̎���敪�ɉ����āA����̌o���܂������������߂āA���ւ̎莆�̒��Ŏ��̂悤�ɃR�����g���Ă���B
"���̎���"
�@�u�R�[�q�[�͔|�̓��W�A�i���̃��x�����E�v���g�𒆐S�ɍs���Ă��܂����B���̓R�[�q�[�_�Ƃ͂���܂���B�v�i���̌�A���S�͐��ֈڂ������j�u�i���̂����W���[���X���ʂł��j���݂̓R�[�q�[�_������邱�Ƃ͂ł��܂���v�i���ʓ��͒��҂��t�L�j�B
�@�Ƃ���ŁA�����d�������Ă����uJATAK�_�ƋZ�p���y�𗬃Z���^�[�v�́A�̂̑�R�[�q�[�_��u�t�@�[���_�E�O�@�^�p���v�̍L��ȕ~�n�̈�p�ɂ���B���̔_��͊}�ˊۈږ��̐l�X�͂��߁A���̌�̑����̓��{�l�ږ��������Ă����Ƃ���ł���B�������A���͌��n������̋u�ˈ�т��قƂ�ǃT�g�E�L�r�ɕ����āA�܂��"�̊C"�̂悤�ł���B���Ă�1�{�̃R�[�q�[�̎�����������Ȃ��B���̒n�����Ĉ�ʂ̃R�[�q�[���������Ƃ͑z�����ł��Ȃ��B�������A�T�g�E�L�r���̉��[���ɁA1984�N�̖����f�����u�t�@�[���_�E�O�@�^�p���v�̊Ǘ��l���~�ՁA�R�[�q�[���I�H��A�_��R�~���j�e�C�[�̉f��فuCINEGUATAPARA�v�Ȃǂ̈�\���������B���Ă̓��킢�����̂��i�ʐ^�j�B
"�J��̎���"
�@�u�T���p�E���B�͌Â��R�[�q�[�̂��߁i���Y�͂��ቺ���j�A�y�n�̗ǂ��p���i�B�ɃR�[�q�[�͈ړ����܂����B���̐A���n��������l�s���܂����B����18�N�ԃW���[���X�ł���Ă��܂������A���ꂩ���ǂ����邩�l�������A���m�̃Z���[�h�ɊS�������܂����B�v
�@�u���̍��͉Ƒ��J�����S�̔_��ł���A��^�R�[�q�[�͔|�҂͂ق�̈ꕔ�ł���܂����B�z�ꐧ�x������Ƃ��͑�n��R�[�q�[�͔|���啔�����߂Ă������̂Ǝv���܂��B�v
�@�����A������͏����ɕs���������Ă����B�W���[���X�͏�ɋC���������A���̂��߂ɃR�[�q�[���̐���͗ǂ������肪�ǂ��Ȃ��B�Z�킪�����A����Ɍ������K�͊g������悤�ɂ��A�����͓y�n�������A�n���������A�ȂǂȂǁB���̎����A�~�i�X�W�F���C�X�B���{�̃Z���[�h�J���v��ɁA1973�N��u���W���Y�Ƒg��������i���Ⓦ�ܘY�����j�͂��̏�������F�߂ĎQ�������肵���B���O�ɏ����Ă���������͗��悵�ē��A���A�J�����E�h�E�p���i�C�[�o�i�~�i�X�E�W�F���C�X�B�j�̒n�ɃR�[�q�[��A�����B
�@�Z���[�h�́A���_���E���A���~�j�E���Z�x�A���������Ȃǂ̂��߂ɁA"�����ꂽ"�i�|���g�K����ucerrado�v�̈Ӗ��j�s�т̒n�Ƃ��Ĕ_�n�ɂȂ�Ȃ������Ƃ���ł���B���̒n�ō앨���͔|����A�R�[�q�[����Ă�Z�p�̓���A�傫�Ȏ��������̃��X�N��������o�c��̋�J�́A����1980�N�ɂi�h�b�`���ƂƂ��Ĕ_�ƋZ�p�J���̌������͂ɔh������āA�Z���Ԃł��邪���݂��Ă����̂ŁA�g�������ē��A�҂̒���̌�������������B
�@����������̌��t�Ƃ��āA������ۂɎc���Ă���̂́u�C�ۂ͕ς����Ȃ��B�������A�y��͕ς�����v�ƌ������Ƃł���B�܂�A�W���[���X��p���i�ł̋C�ۍЊQ�͐l�דI�ȓw�͂�ς�ł��������Ȃ��B�Z���[�h�̓y������͈������A����͎����̋Z�p�E�o�c�̍H�v�E�w�͂ɂ���č������Ă݂���ƌ�������̐錾�ł������̂ł���B
�@�Z���[�h�ł́A���܂ł̔엀�ȓy�n�ł̃R�[�q�[���Y�Z�p�Ƃ͂܂�ňقȂ�"�y���"�Z�p���K�v�ł������B�܂������āA���������������A�K�͊g��ɔ����y�n���p�E��ƃV�X�e���Ǘ��Z�p�A���u�E�ƒn�̐V�Y�n����̗��ʁE�̔��헪�J���ȂǁA����̏��i���Y�_�ƌo�c�̕s���̑����̉ۑ�Ɏ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ނ̌Z��o�c�u�t�@�[���_�E�p���C�[�]�v�͂��������ʂ����i�V���T�J�_��̎ʐ^�j�B
"����̎���"
�@�u�p���i�B�͂��т��ё��̔�Q������A�R�[�q�[���i���Ⴉ�����B�Z���[�h�J����10�N�o���A�Z���[�h�ł̃R�[�q�[���Y���O���ɏ��n�߂āA���̔�Q�����Ȃ����Ƃ���A80�N��ɂȂ�ƁA��̃T���p�E����p���i���瑽���̐l�������Ă��܂����B
�@�L�[�R�[�q�[�̂��̎���̏��i�̌���������������u�{�A�E�G�X�y�����T�_���v�̃��X�i�J����́A1984�N�Ƀp���i���痈�āA�����e�E�J�����C���ɓ����Ă��܂��B�v
"���n�̎���"
�@�u�Z���[�h�̋C�ہE�y��ȂǂɑΉ�����Z�p���m������Ă��āA�i���̗ǂ��R�[�q�[���o����悤�ɂȂ�܂����B���̎�����ے����铤����������u�o�E�[�_��v�̕��c�x�Y����́A�Z���[�h�R�[�q�[���Y�҂̑�\�I�Ȑl���ł��B
�@���̒�A�w�̗F�B�ł���A�T�����[�}�������߂Ĕ_��ɗ��āA1�N������R�[�q�[���n�߂��̂ł��B1984�N�ɂ̓J�������40�L���̂Ƃ���ɓy�n���w�����ăR�[�q�[�����J���܂����B��ςȓw�͉Ƃł���A���Ƃł���܂��B�c7�`8�N�O����A���{�̊�ƂƔ̔��_�܂����B�Z���[�h�n�т̃R�[�q�[���Y�҂͑����̂ł����A�_����ɗA�o�ł���܂ł̒����E���I�ݔ��������Ă���l�͏��Ȃ��ł��B���o��"���Ԃ�"�ł͂���܂��A�ǂ��������܂Ŋ撣�ꂽ�ƁA���c����͎��̌ւ�ł���܂��B�v
�R�[�q�[�̕��Q�̗��͏I���̂��H�@�ǂ��֍s���̂��H
�@�Ƃ���ŁA�Z���[�h�܂ŕ��Q�̗������Ă����R�[�q�[�́A�������u�J�i���̒n�v�i�����C���܂悦��_�̖��̗�������"�̒n"�j�Ƃ��ė��������Đ��n�̎��������Ƒ�����̂��낤���H�@���Ă̎��D�_�@�ƈ���āA�Z���[�h�ł͓y��E�a�Q���̊Ǘ��A�͔|���璲���E�I�ʁE�o�ׂ܂ł̋@�B���V�X�e���̊m���Ȃǂ̏W��Ǘ����s���Ă���B���������āA�̂̂悤�ɎY�n��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ̒n�͎��D�͋N����Ȃ��̂�������Ȃ��B
�@�������A���₳��́A���܂ł̔����I�ɂ킽��h�͐����̃R�[�q�[�l����U��Ԃ�A�Ђ����ɔY��ł���悤�Ɏv����B�u�t�@�[���_�E�p���C�[�]�v���͂��߁A�Z���[�h�̃R�[�q�[���Y�E�̔��͔ɉh���A���܂⌎�͖����Ă���B�������A���₳��͖����ɔE�ъ��e�������Ă���̂�������Ȃ��B���̒�����Ƃ����炻��͉��Ȃ̂��낤���H�@�����āA�R�[�q�[���܂����ɏo��Ƃ�����A�ǂ���ڎw���̂��낤���H
�@������������A�k�サ�ăo�C�A�B�̊����n�т̍��n�Ŋ������݂Ȃ���ꎞ���߂������Ƃł����邩������Ȃ��B����Ȏv��������Ȃ���A���₳��ƈꏏ�Ƀo�C�A�̍��n�𗷂������Ƃ�����B�����ɂ͍��܂łƂ͈Ⴄ�����n���_�Ƃ̔_�@�����܂�������B���ɂ͋����[�������B������A�����Ō������ƁA���������Ƃ����|�[�g�������Ǝv���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����_�H��w���_�����A�V�P���F���J�N�v�j
�i���z�[���y�[�W�ɂ͎ʐ^�͌f�ڂ���Ă��܂���B�j
|