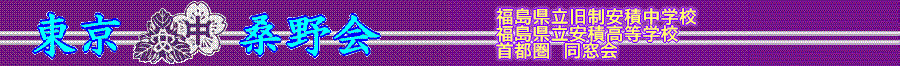
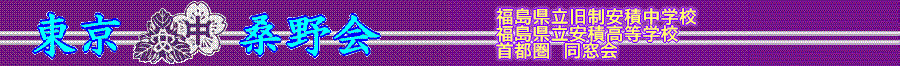
| 芥川賞作家からの特別寄稿 | |||||
|
|
|||||
 88期 玄侑宗久 |
2024.04.15 紫の旗ゆくところ 玄侑宗久(88期) 第125回芥川賞受賞、臨済宗妙心寺派・福聚寺 住職 高校時代のことは、これまでまともに書いたこともないし書こうと思ったこともない。今に繋がる都合のいい話ばかりになるような気がして、恐ろしいのだ。渾沌としたあの時代を、いい加減に描いて台無しにしたくはない。書いてしまったことはおそらく現実以上にリアルになり、愛すべき渾沌を失う可能性もある。それは『荘子』の渾沌が勝手に目鼻口を付けられ、ついに死んでしまった話のようではないか。今回の原稿、お引き受けしたからには渾沌に向き合う覚悟だが、用心深く穴を開け、渾沌が元気になるのを確認したあたりで筆を擱きたい。そんな心づもりである。 まず何より嘘偽りなく言えるのは、安高の入学式当日、私は2、3年生の歌う校歌と応援歌に、それまで味わったことのない感動を覚えた。背骨の中を電流が走り、文字どおり痺れた。 当時からずっと、それは野太い男声合唱のせいだと考えていた。しかし最近は、音程の誤差を鷹揚に包み込む読経の如きポリフォニーのせいかと思ったりもする。まぁいずれにせよ、大河の流れのような安心と鼓舞とを、私はその後も同じ歌声に聞き取り、自分も歌いながら確認していたのである。 居並ぶ先生方がまたジグザグで面白かった。ジグザグとは、もしもアドラーの言うように、縦と横の人間関係があるとするなら、その縦・横・斜め加減がジグザグなのだ。上から目線で話す先生も無論いたが、なかには自分の研究に没頭しているのか、申し訳なさそうに上目で生徒を見る先生もいた。1年のときの担任は竹花栄明先生で、とにかく自分の専門の中国史がお好きらしく、世界史の授業では秋になっても中国史が終わらず、中国以外の世界についてはあからさまにスキップした。 しかし竹花先生が毎年年賀状を下さり、励ましの言葉を書き送りつづけて下さったのには驚いた。結婚式に祝辞をお願いすると、それ以後は年賀状ではなく結婚記念日にはがきが届くようになり、それは先生が亡くなる前の年まで続いた。間違いなく先生は、私の人生に大きく影響するような気長な関わりを、意志的に持ってくださったのである。 詳しく一々書くわけにはいかないが、安高は先生方の博覧会場だった。「同じ先生」という括りのなかに、これだけのバラエティがある。学校祭のために映画を作りたいという生徒たちにそれを認め、2ヶ月は欠席してもいいと言い放った先生。トイレで喫煙の残り香を嗅ぎ、全校集会で「もっとうまくやれ」と叱咤した生徒指導の先生。そして試験のとき答案用紙を裏返し、びっしりと勝手な意見を書いた私に、80点をくれた地理の先生。私の入学する前年くらいに下駄履き通学は禁じられていたものの、バンカラの気風が当時は色濃く残っていた。バンカラとはたぶん、粗末で粗野な外見のなかに崇高な精神を育む文化なのだ。おそらくそうした破調でないと収まりきれない渾沌が、安高生には横溢していたのだろう。 教室には、不穏なエネルギーを秘めた面々が犇めいていた。或いはサッカーに明け暮れ、或いはフランス語を学び、なかには小説を書いている人もいて、確か二年のときに260枚の作品を書き上げた。それは驚歎すべきことで、皆それぞれの将来に直接は繋がらないことに没頭し、豊かな時間を過ごしていた。警察に一番世話になった人がその後県警本部の偉い警官になったのは驚いたが、ことほど左様に渾沌は何でも生みだすのである。 私自身の渾沌は、やはり寺に生まれながら僧侶になりたくはない、という思いが多くを占めていた。剣道に打ち込む一方で、小説や禅についての本も読み、すべてが中途半端なまま将来の見えない憂いばかりが募り、それは20代半ばすぎまで続いた。だから20代は憶いだしたくもないが、安高時代は些か違う。戻れない聖域とでも言うべきか……。作家になる、という漠たる思いも、その濃密な渾沌のなかから芽吹いたのだった。 ふと、「紫の旗ゆくところ」を憶いだす。歌う者を奮い立たせ、勝利に向かわせる歌だが、どう考えても「紫」は勝利の色と思えない。儒教が嫌い、道教が好むこの色は、渾沌を包み込む色だ。 ※) 本稿は、東京桑野会会報No.46号に寄稿された文書を転載したものです |
||||
| 前頁に 戻 る |
|||||